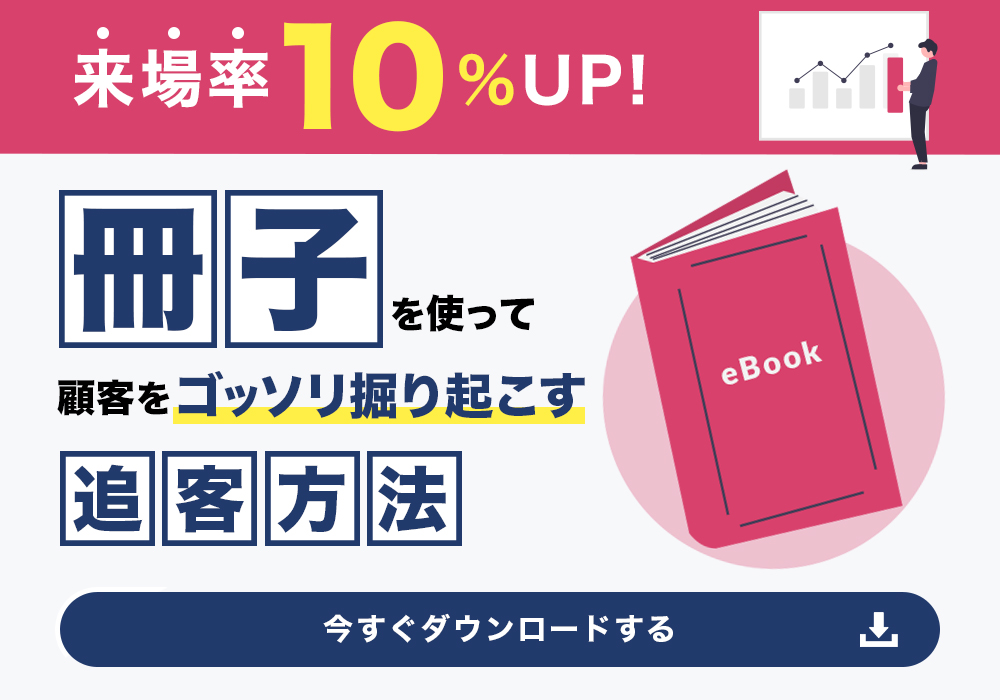記事コンテンツの作り方次第で大きく成果が変わる!コンテンツマーケティングの基本
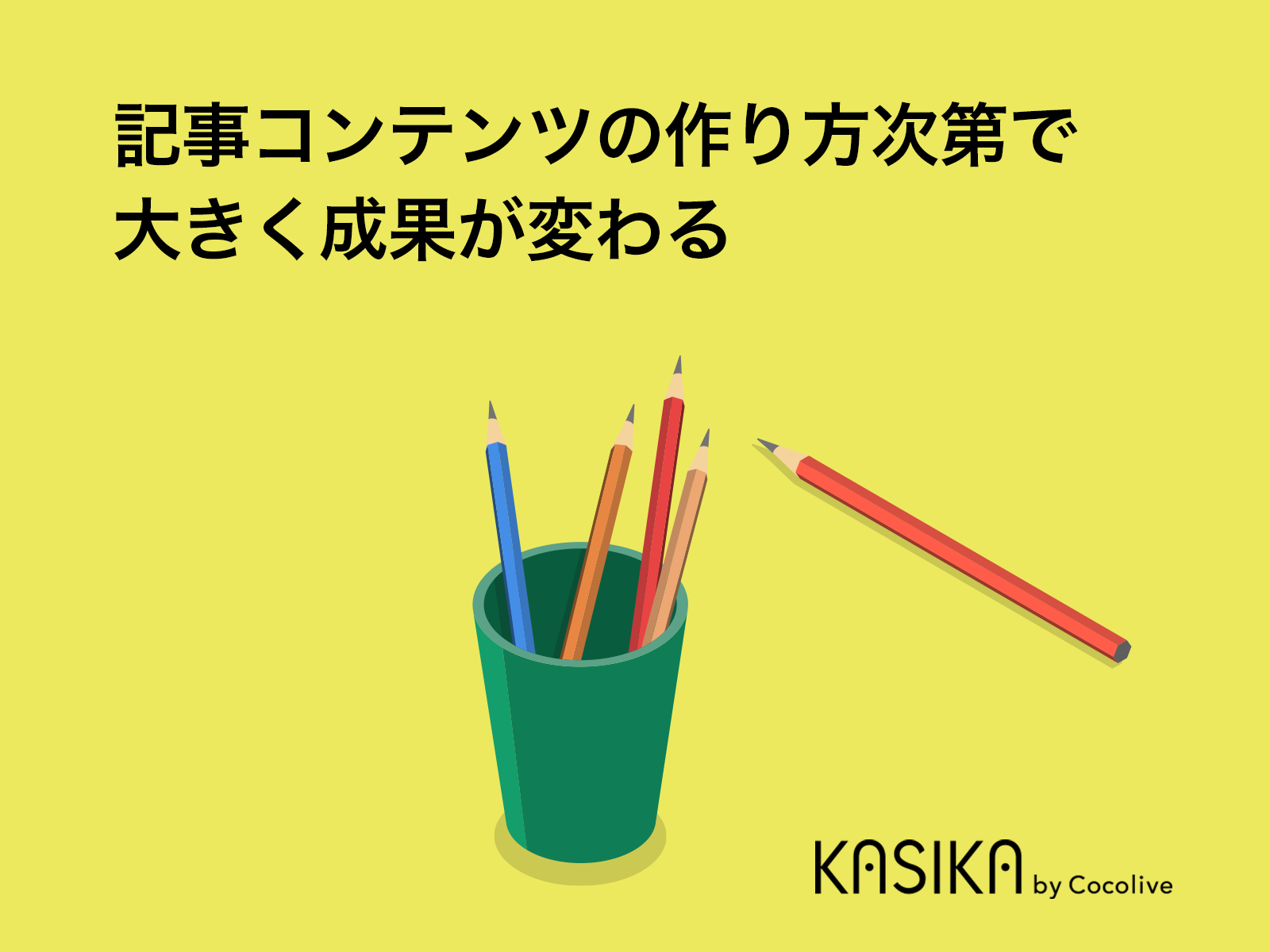
さまざまな手法があるコンテンツマーケティングですが、現在では「記事コンテンツ」の作成が主流となっています。
この流れに伴い、昨今では記事コンテンツの制作・提供に取り組む会社が増えてきていますが、記事コンテンツの作り方には気を付けるべきポイントがあります。
本記事では、それらのポイントを整理し、「読み手に響く記事コンテンツ」の作り方を解説します。
読み手に響かない記事コンテンツとは
コンテンツマーケティングにおいて重要なことは、「価値あるコンテンツを提供していくこと」です。
しかし、作り方によっては、読み手にとって価値のないものが出来上がってしまうケースも少なくありません。
よくある失敗例を通して、注意点を整理していきましょう。
自分よがりな記事になっている
伝えたいことが多いため、ついつい「伝えたい情報」ばかりをコンテンツに盛り込んでしまうケースがよく見られます。
これだと、読み手目線での「価値あるコンテンツ」を作ることはできません。
[memo title=”MEMO”]例として、イベントやモデルハウスへの来場を強く伝えようとするあまり、売り込み色が強いものになってしまうコンテンツなどが挙げられます。
これだとせっかくのコンテンツも広告と何ら変わらないものとなってしまいます。[/memo]
専門用語が多用されている
業界用語・専門用語の使用についても注意が必要です。
知っている側からすると当たり前に感じてしまう業界用語・専門用語ですが、読み手にとっては難解なものと捉えられてしまう恐れがあります。これらを多用してしまうと、読み手の理解は得られず、しっかりと内容を伝えることができません。
[box class=”box29″ title=”point”]読み手の目線に立って「悩みを解消してあげられるコンテンツ」を目指し、意味が伝わる表現で作るようにしましょう。[/box]
誰を対象にして書いているかがわからない
「価値あるコンテンツ」の内容は、当たり前すぎる情報ばかりではいけません。
どういったターゲットに届けたいコンテンツなのかを明確にし、特定の読み手に「刺さる」コンテンツを作成しましょう。
[say name=”Cocolive 手塚” img=”https://cocolive.co.jp/newsite/wp-content/uploads/2019/03/97b620e0db1335a30d2fb9333aa91329.jpg”]ターゲットを具体的にしておくことで、読み手にとって得るものが多いコンテンツ作りがしやすくなるでしょう。[/say]
[alert title=”注意”]対象を定めず万人受けするコンテンツを目指してしまうと、どこにでもあるような漠然とした情報となり、価値の少ない記事コンテンツとなってしまいます。[/alert]
[memo title=”MEMO”]響くコンテンツについてさらに詳しく知りたい方は「お客様に響く記事の書き方|コンテンツマーケティングの鉄則!」をお読みください。
[kanren id=”1008″][/memo]
記事作成の基本は「誰に・何を伝えて・どうなって欲しいのか」しっかりと考えること
前の段落ではよくある失敗例をもとに注意点をご説明しましたが、それを踏まえて、記事作成の基本ポイントを整理していきましょう。
[say name=”Cocolive 手塚” img=”https://cocolive.co.jp/newsite/wp-content/uploads/2019/03/97b620e0db1335a30d2fb9333aa91329.jpg”]コンテンツを作成する際は、常に下記4点を意識することが重要です。[/say]
ターゲットを作る
失敗例でも説明しましたが、コンテンツを届けるべきターゲットを明確にしておきましょう。
[alert title=”注意”]ターゲットを具体的にしておかないと、伝える範囲が広くなりすぎてしまい、内容の薄い記事になってしまう恐れがあります。[/alert]
ターゲットは「何を知りたいか」を徹底的に考える
ターゲットを定めたら、そのターゲットがどういった情報を求めているかを細かく考えるようにしましょう。
これこそが、コンテンツ作成に於いて重要な「読み手の目線に立つ」ということです。
[box class=”box29″ title=”point”]ターゲットとなる読み手がどのような悩みや疑問を持ち、どのような情報を求めているかなどを具体的にイメージしていくと良いでしょう。[/box]
どのような構成で伝えるのが一番理解してもらえるか考える
伝えるべき内容が決まったら、その内容をどういった構成で伝えていくかを整理しましょう。
[alert title=”注意”]伝えたい・伝えるべき内容も、理解を得られないと意味がありません。
最終的に届けたいコンテンツ内容を理解してもらう上で、先に説明しておくべき情報は無いかなど、理解しやすい順序や構成を考えて行く必要があります。[/alert]
どのような表現で伝えるべきか考える
最後に、コンテンツの表現方法です。
同じ内容を伝える場合でも、表現が変われば受け取り方が変わります。先述した専門用語の多用のように、意味は同じでも難しい言葉を使ってしまっては、十分な理解を得られません。
使用する言葉などにも気を配り、また表現の統一感も意識することで、全体を通して違和感のないコンテンツを作ることもポイントです。
[memo title=”MEMO”]コンテンツマーケティングの全体的な知識は「コンテンツマーケティング一覧」よりお探しください。[/memo]
まとめ
記事コンテンツを作る経験がある方はそう多くはないと思います。
最初はなかなか苦戦してしまうかもしれませんが、受け取る側の立場に立ってじっくりと考えることで、価値のある・良いコンテンツとはどういったものかが見えてくるかと思います。
[say name=”Cocolive 手塚” img=”https://cocolive.co.jp/newsite/wp-content/uploads/2019/03/97b620e0db1335a30d2fb9333aa91329.jpg”]ポイントを押さえて、読み手に喜んでもらえるコンテンツ作りを目指していきましょう。[/say]